「メニエール病と首・肩の痛み、どうアプローチすべきか?」
メニエール病は耳鳴りやめまい、不眠といった自律神経の乱れを伴う症状が特徴です。特に、慢性的な首・肩の痛みや体の緊張が強いと、交感神経が優位になりやすく、症状が悪化するケースが多く見られます。
このケースでは、筋肉や関節だけでなく、「神経伝達」や「自律神経バランス」にも着目することが重要でした。
実際の評価と施術をもとに、**「どこに原因があるのか?」「どこを調整すれば楽になるのか?」**を整理し、施術の流れを解説していきます。
1. スタッフからの質問(患者の状況)
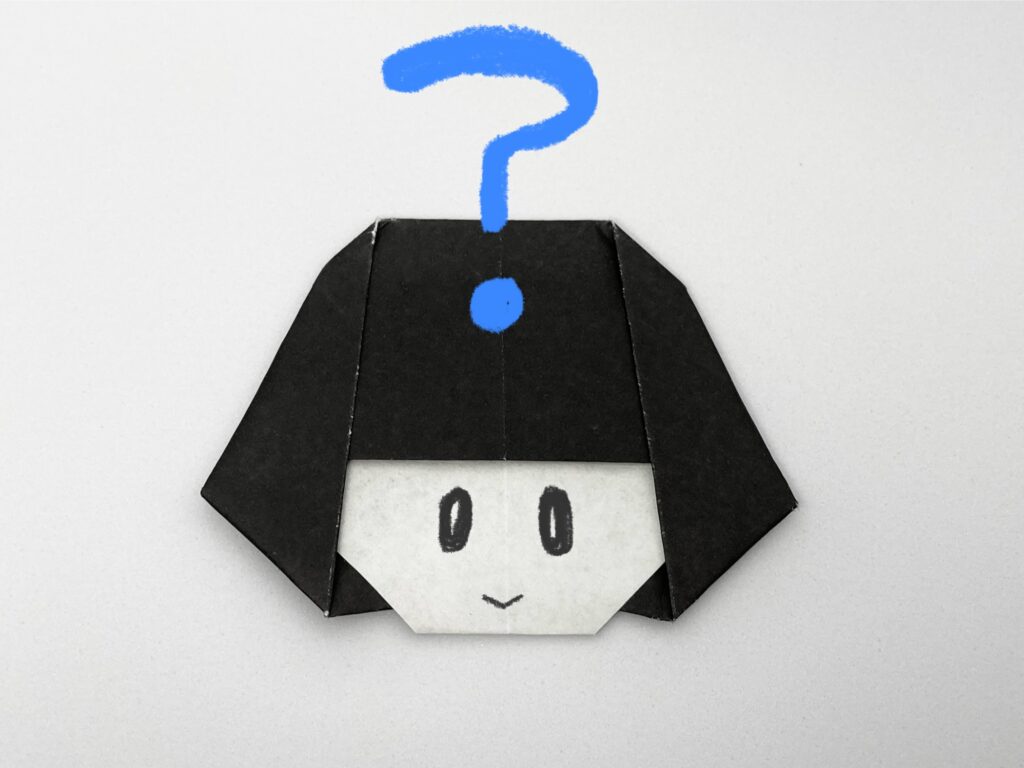
Q. 50代女性の患者様が、首・肩の痛みとメニエール病(耳鳴り・不眠)で悩んでいます。
過去に子宮筋腫の手術と左下腿の骨折歴があり、これらが影響している可能性もあります。
自律神経の乱れが強く、通常のストレッチや電気治療では改善が見られません。
施術と運動指導のポイントを教えてください。
2. スタッフの見解
「首・肩の痛みを軽減するために、僧帽筋への電気療法とストレッチ指導を行いましたが、大きな改善は見られませんでした。何か別のアプローチが必要なのか、詳しく知りたいです。」
3. スタッフカウンセリング(問診・検査結果)
✅ 動作時症状と可動域制限
- 僧帽筋の安静時痛・可動時痛・圧痛(+)
- 頸椎の前屈・後屈・回旋時に痛み(+)
- 体幹の前屈・後屈時に背部痛(+)
- 胸椎・股関節の可動域制限
✅ その他の検査結果
- 左上肢および肩甲胸郭の筋力低下(MMT-)
- 左下肢の筋力低下(MMT-)
- 肩上部〜腰部にかけて代償動作(感作・力み)(+)
4. 採用評価(田中院長の見解)

この患者の痛みや自律神経の乱れの根本原因は、以下の3点が大きく影響していると考えられる。
① 体幹の安定性低下(腹腔内圧の低下)
→ 腹圧が低下し、全身の緊張が抜けず、自律神経の切り替えができていない
② 胸椎・股関節の可動域制限
→ 胸郭・股関節が硬く、肩・腰に負担が集中
③ 過去の手術や骨折による神経伝達の乱れ
→ 手術痕(腹部)が神経伝達を妨げ、正常な動作ができていない
→ 左足の接地安定性の低下が体幹の崩れを引き起こしている
▶ 施術では、「首・肩を直接治療する」のではなく、「神経伝達と動作の改善」をメインにアプローチする必要がある。
5. 施術内容(アプローチと手技)
① 腹圧の向上(5分) → 体幹の安定化
・呼吸誘導(腹式呼吸の再学習)
・微弱電流を用いた腹部の筋緊張調整
■ 何がどうなったらOK?
☑ 呼吸が深くなり、力みが抜ける
☑ 施術後に体の安定感が増し、痛みが軽減する
② 胸郭&股関節の可動域改善(7分) → モビライゼーション
・ 胸椎モビライゼーション(胸郭の回旋誘導)
・ 股関節モビライゼーション(股関節の内外旋ストレッチ)
■ 何がどうなったらOK?
☑ 胸郭の可動域が増え、肩・腰の負担が軽減する
☑ 股関節の詰まりが軽減し、動きがスムーズになる
③ 足底感覚の再教育(5分) → 接地感の回復
・ 足底タッピングで接地感覚を再教育
・ 片足立ちでのバランストレーニング
■ 何がどうなったらOK?
☑ かかと~母指球まで均等に接地できる
☑ 立位バランスが安定し、力みが軽減する
④ 自律神経調整(7分) → 微弱電流による内耳神経のアプローチ
・ 耳鳴り・不眠の改善を目的に、微弱電流で内耳神経を調整
・ 施術後、深いリラックス状態が得られる
6. お客様への説明(患者教育)
「痛みやメニエール病の原因は、首や耳だけの問題ではなく、全身の使い方や神経の働きのバランスの乱れにあります。」
「施術では、腹圧の安定・胸郭と股関節の動きの改善・足底感覚の再教育を行い、根本的に体を整えていきます。」
7. 通院計画とセルフケアの指導
📅 2週間プラン(週2回の施術+ホームケア)
1週目: 腹圧の安定と可動域の改善
2週目: 足底バランスの改善と自律神経の調整

まとめ & メッセージ
今回のケースでは、メニエール病による耳鳴り・不眠、そして首・肩の痛みが主訴でした。しかし、問題の本質は単なる筋肉のこわばりではなく、自律神経の乱れや過去の手術・骨折の影響が複雑に関係していました。
ポイントとなったアプローチ
- 呼吸と腹圧の調整 … 体幹の安定化と全身の緊張の軽減
- 胸郭・股関節の可動域改善 … 過度な負担を減らし、スムーズな動作へ
- 足底感覚の再教育 … 接地の安定化による姿勢の改善
- 自律神経の調整 … 過剰な交感神経の働きを抑え、リラックスしやすい状態へ
「首・肩が痛いから、そこをほぐせばいい」という対症療法では、一時的な改善にとどまってしまいます。根本的な解決には、体全体のバランスと神経の働きを見直すことが不可欠です。

コメント